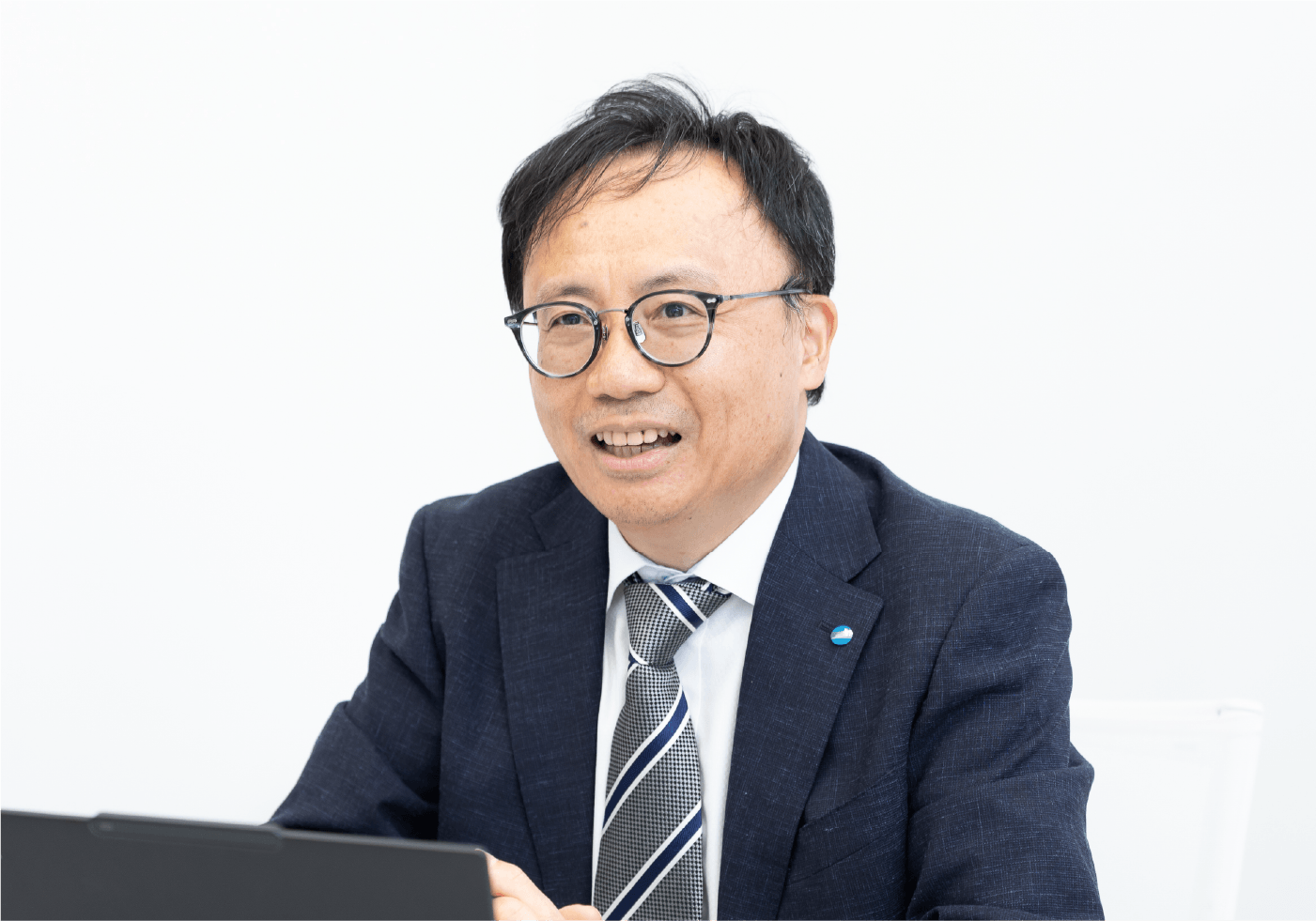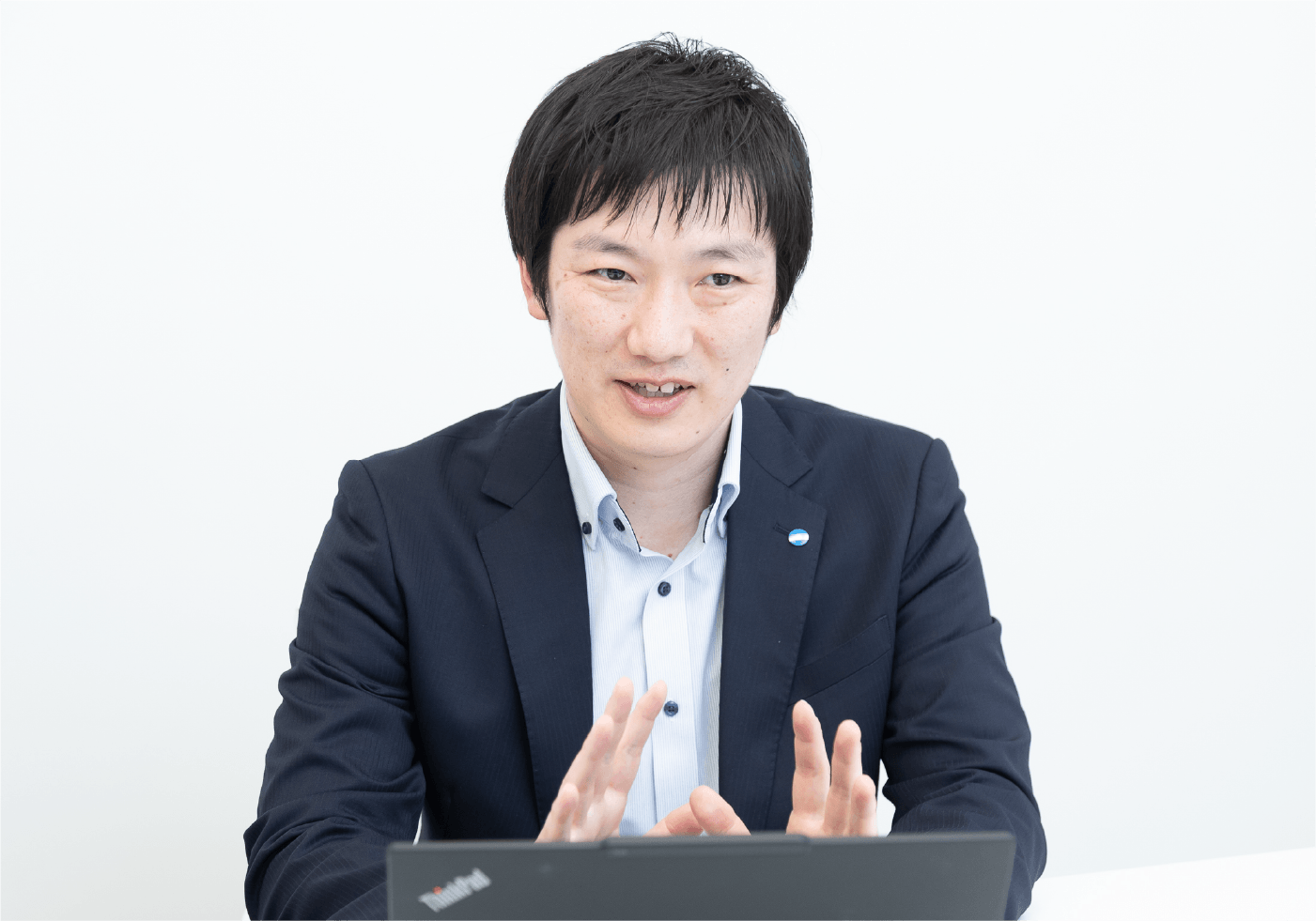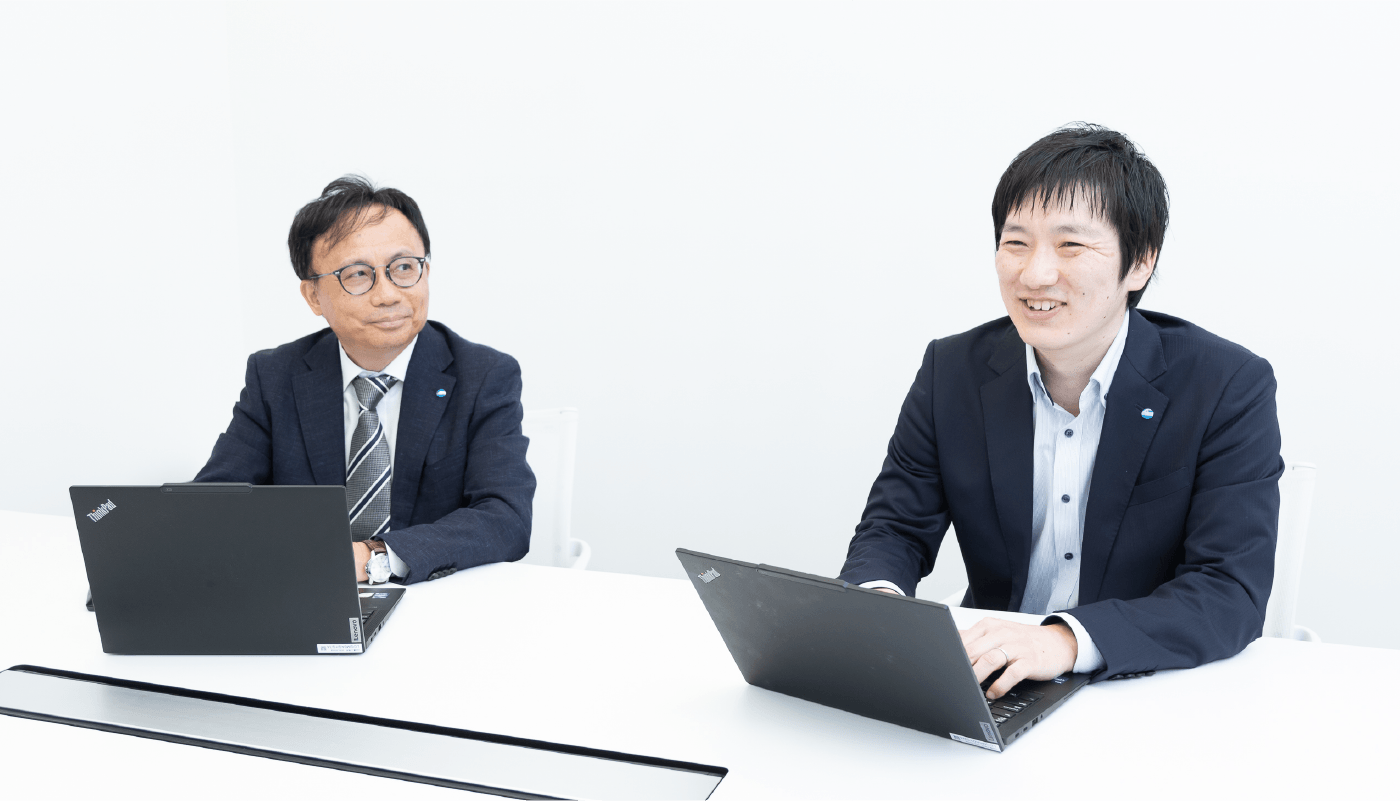広報ブログ「Imaging Insight」を開設する前は、メディア向けの情報発信手段にどのような課題感があったのでしょうか。
安部氏日頃のニュースリリースや記者発表会だけでは伝えきれない情報があるとは感じていました。ところが、どのような内容だと興味を持ってもらえるのか、その手段をどうするのか、なかなかよい解が見つかりませんでした。これは当社に限らず広報部門の共通の課題だと思います。
ニュースリリースは世の中にない新しい情報をお届けする大事な使命を担っていますが、一方で新しくないものにお伝えする価値がないのかと言えば、そんなことはありません。また、ニュースリリースには一定の形式や分量などの制約があります。書かれた内容がどれだけ理解され、メディアを含め一体どれだけの方々にエンゲージメントできているのか、なかなか推し量るのが難しい。そうした課題の解決策の 1つに浮上したのが、広報ブログというオウンドメディアの導入だったのです。
開設を決断した決め手は何だったでしょうか。
安部氏オウンドメディアであればニュースリリースで扱えなかった内容であっても、またすでに報道された内容であっても、重要な話題として切り口を考えて記事化することができます。その話題に関する興味深い背景や経緯、当事者の生の声などを紹介したり、また市場動向や技術のポイントを押さえた解説を含めたりすることも可能です。毎月のアクセス実績を見ることでどれだけ読まれているかも把握できます。
広報部内で議論した結果、メディアの取材誘致に役立つに違いないと考えたこと、加えてメディア以外にも多くのステークホルダーの方々に理解されやすく、価値ある情報の伝え方ができると判断したことが大きいですね。
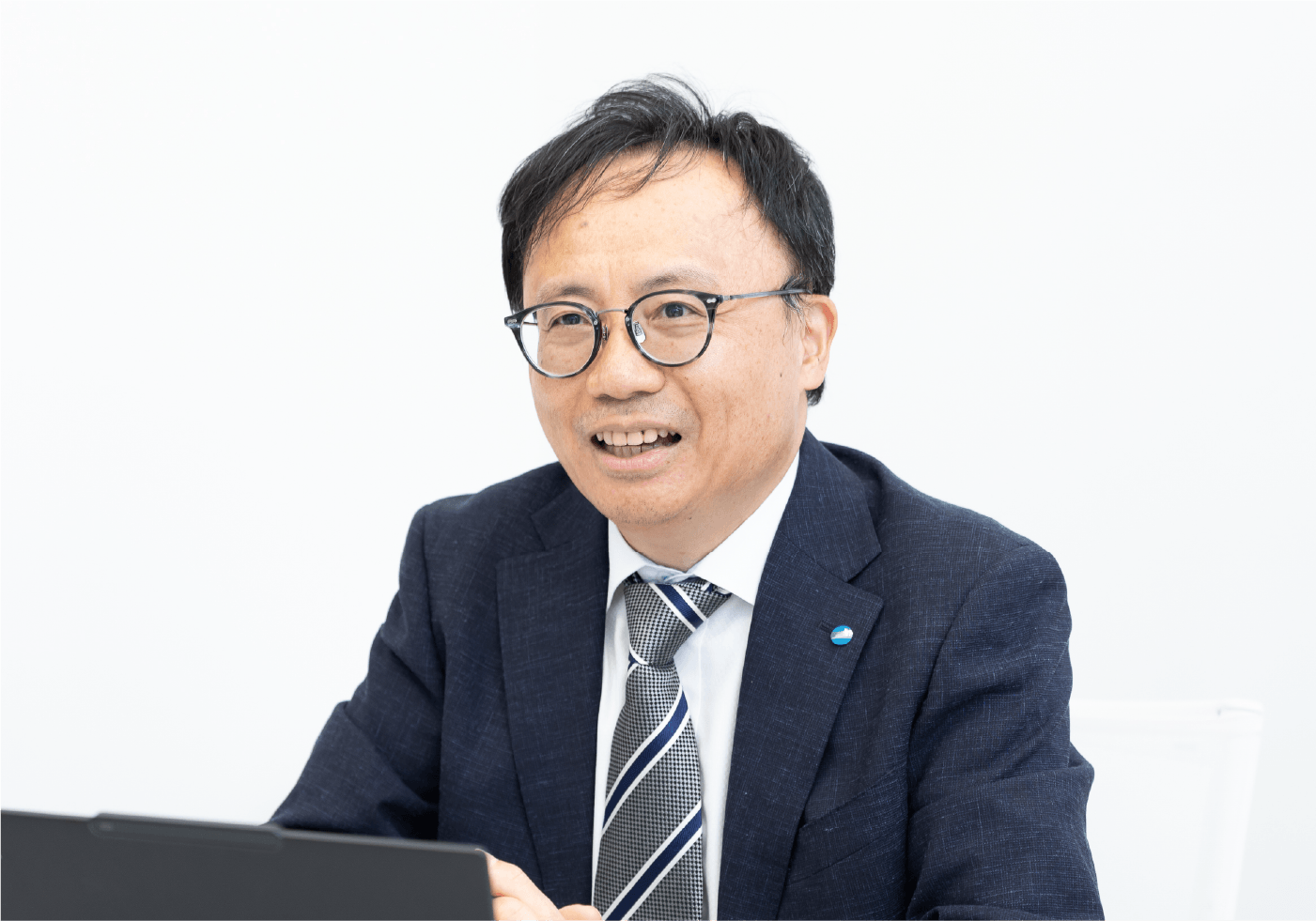 「Imaging Insight」編集長の安部寬氏
「Imaging Insight」編集長の安部寬氏
企画テーマは
会社のマテリアリティを軸に
開設までに苦心されたことはありましたか。
安部氏私が本格的に参画したのは、ブログの基本構想ができた後の22年の年明け頃で、開設予定の3か月ほど前でした。実際に編集長に任命されてから残った難題を仕上げ、開設にこぎ着けたのですが、その間はまさに産みの苦しみに近いものがあったのを思い出します。
一番は、ブログ記事の基盤となるものをどう定めるか、という点でした。掲載していく一つひとつの記事を貫く、キーとなるメッセージの導入が必要だと考えたのです。それを何にするかについて最も悩みました。
当社は2030年の社会課題を想定し、それらの解決へ向けて当社が提供すべき社会価値を明確化し、「5つのマテリアリティ」を特定しています。それを軸に記事を揃えていこうと決めたとき、思案していたブログの骨格が固まりました。
メディアのコンセプトを一瞬で伝えるために名称も大事かと思います。「Imaging Insight」という名称はどのように決められたのですか。
安部氏Imagingは当社の経営ビジョン「Imaging to the People」でも使われており、創業以来カメラや写真、画像処理を中心に事業を展開してきた私たちのDNAを象徴するキーワードとして外せませんでした。また、Insightは、ブログの目的として、記事を読まれたメディアの方が取材のヒントや発見につながればいいという思いを込めています。
ブログ記事の企画立案、社内における説明や調整はどのように進めているのですか。
安部氏企画の考え方としては、大きくは中期経営計画に提示した強化事業や収益堅守事業に注力しながら、経営基盤として強みとなる人財育成、知的財産、環境対策などの事例を含めてテーマを検討しています。関係部門にはブログの価値を示しながらタイミングを図って取材依頼をかけています。
月次のアクセスデータやメディア掲載実績が揃ってきて、社内への説明をしやすくなったことは確かです。でも、それより現場の社員は自分の活動を知って欲しいという思いを元々持っており、私たちの取材にはいつも好意的に協力してもらっています。
当社の多岐に渡る人財も今までの広報活動では社外に紹介する機会に必ずしも恵まれなかったかもしれませんが、Imaging Insightを通して彼らの生の声や熱い思いをお伝えできると考えています。
社内啓発の方はできることがまだ残っていますが、ブログ記事がアップされると直接の関係者からだけでなく社内のあちこちからアクセスされ、認知が進んでいる印象を持っています。
 コニカミノルタの広報ブログ「Imaging Insight」
コニカミノルタの広報ブログ「Imaging Insight」
読み物としてストーリーを
伝えることの効果
ブログ開設から2年半ほど。運営の成果やご評価をお聞かせください。
安部氏お陰さまでページビュー(PV)、ユニークブラウザ(UB)数も右肩上がりで推移しており、取材の申し込みも複数件ありました。今後も期待できる成果で、すでに本来の目的の相当程度は達成できていると考えています。なにしろ初めての取り組みでしたから手探りで進めてきた面もありますが、やってきたことは間違っていなかったと認識しているところです。
メディアの取材誘致という当初の目的以外にも、多様な方面から反響がありました。例えば、他業種の企業や大学などの研究機関からの反応もあり、また、社内外のコミュニケーション改善にも役立っています。
月次で報告いただいているレポートから、サイトや記事の様々なアクセスデータを確認できるのも励みになります。新たな発見や次のテーマにつながる気付きも得られます。長期間高いPVを維持するロングテールの記事も少なくなく、それはほかの形ではなし得ない読み物としての魅力を発しているからでしょう。新たな読者にずっと読まれ続けるのはブログ記事ならではの特性だと思います。
西上氏は後からImaging Insightの企画・編集に加わったお立場ですね。どのような感想を抱かれたでしょうか。
西上氏オウンドメディアという情報チャネルの取り組みに参加して、ニュースリリースのように最新の瞬間だけを切り取るのではなくて、ニュースができ上がるまでのベースとなる活動をストーリー立ててお伝えできるのは面白いと感じました。
例えば、私が加わる1年も前に掲載された生成AI関連のブログ記事がずっと読まれ続けているのには目を見張りました。長期間にわたってメディアに関心を持ってもらえる活動は、とても価値あると思います。長期間読まれている記事はほかに幾つもあるので、今後の反応が楽しみです。
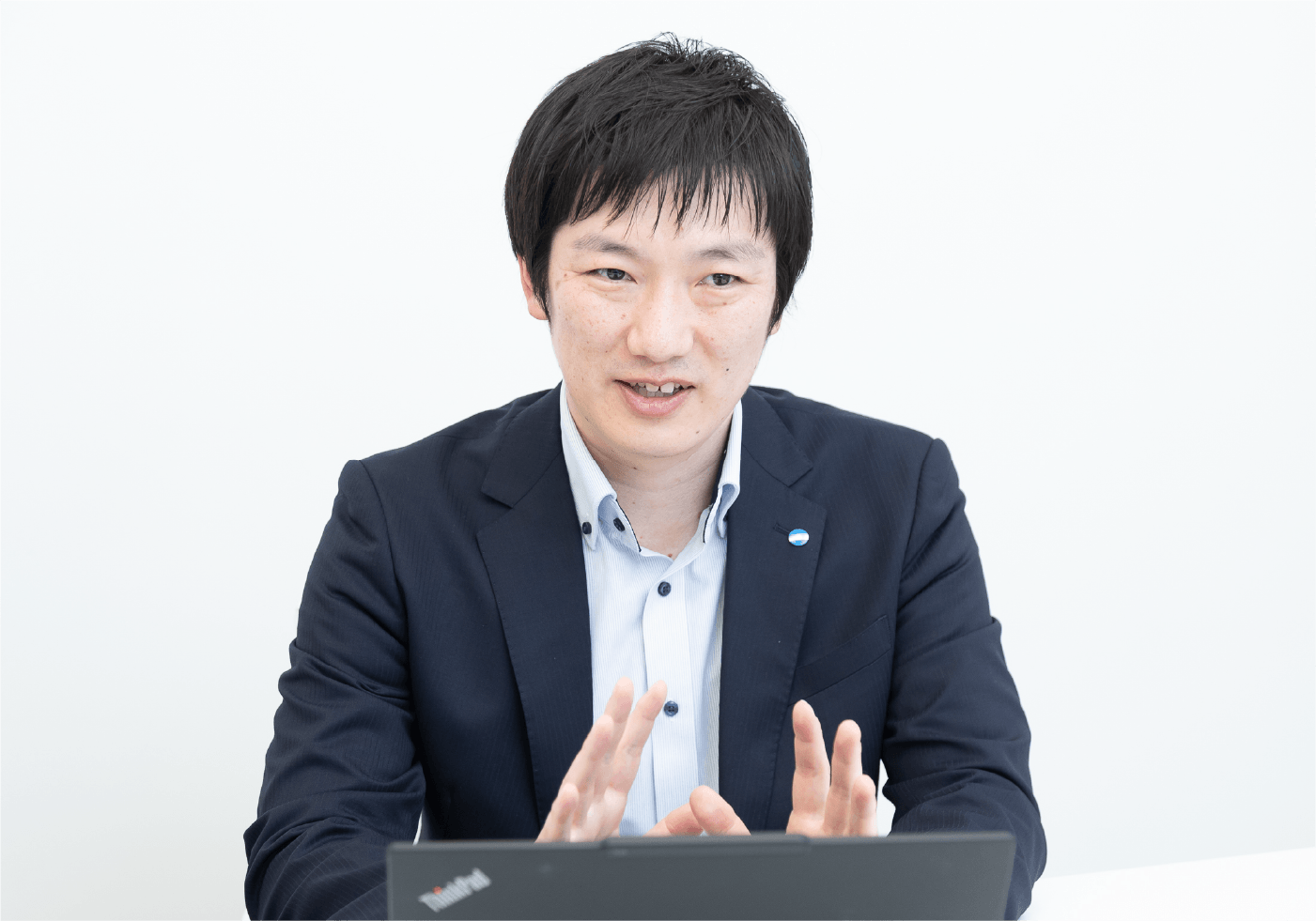 安部編集長と共に「Imaging Insight」を運営する西上直孝氏
安部編集長と共に「Imaging Insight」を運営する西上直孝氏
メディア掲載はもちろん
思わぬ副産物も
広報ブログの手応えを感じた、具体的な収穫がありましたら紹介ください。
安部氏いま西上が紹介したとおり生成AIの記事がロングテールで読まれているというデータを見て、読者の関心がより高いものを届けようと考え、続編を企画しました。ちょうどその頃生成AIの活用を推進する社内イベントがあり、それを事例としたブログ記事を掲載しました。すると予想以上に大きな反響が起こり、大手メディアからも取材依頼を受け、記事化に至りました。ねらい通りの展開になりまして、広報ブログの効果を実感した次第です。
メディア掲載以外の副産物もあって、ブログ記事を読んだ某大手シンクタンクからの依頼で、彼らが主旨するセミナーにブログで紹介した人財として当社社員が登壇したこともあります。そのセミナー登壇からも次へのアクションにつながっており、結果として副産物以上の収穫だったと言えます。
西上氏そのブログ企画には私も関わったのですが、私にとって少々想定外の出来事がありました。大手メディアに掲載された記事を読んだ外部のAI研究者から、本人に話を聞きたいと連絡が入ったのです。ブログ記事が外部との技術連携にもつながるきっかけになることは驚きでした。広報活動でやってきた取材のインキュベーションとは異なる形の情報発信効果だと感じました。
特にエンジニアについて言えることですが、現場のタレントを見せることで、その人と協働したい、その人と一緒に働きたいという思いに応える機会をつくれるのも広報ブログの面白さだと思います。
現場で活躍する人物を通して会社の強みを紹介することもできるのですね。
安部氏開設からの2年半を振り返りますと、オウンドメディアの基盤はすでに固められたと考えています。そして、ブログへの登場者の考え方や熱い思いを直接ストレートに伝えられるメディアに育っています。これはニュースリリースや、かしこまった発表会ではなかなかできなかったことです。今後も、様々な現場で奮闘している人財を紹介していきたいと思います。それが本人のモチベーションアップにもなり、社内活性化にもつながるという、意義深い取り組みになるはずです。
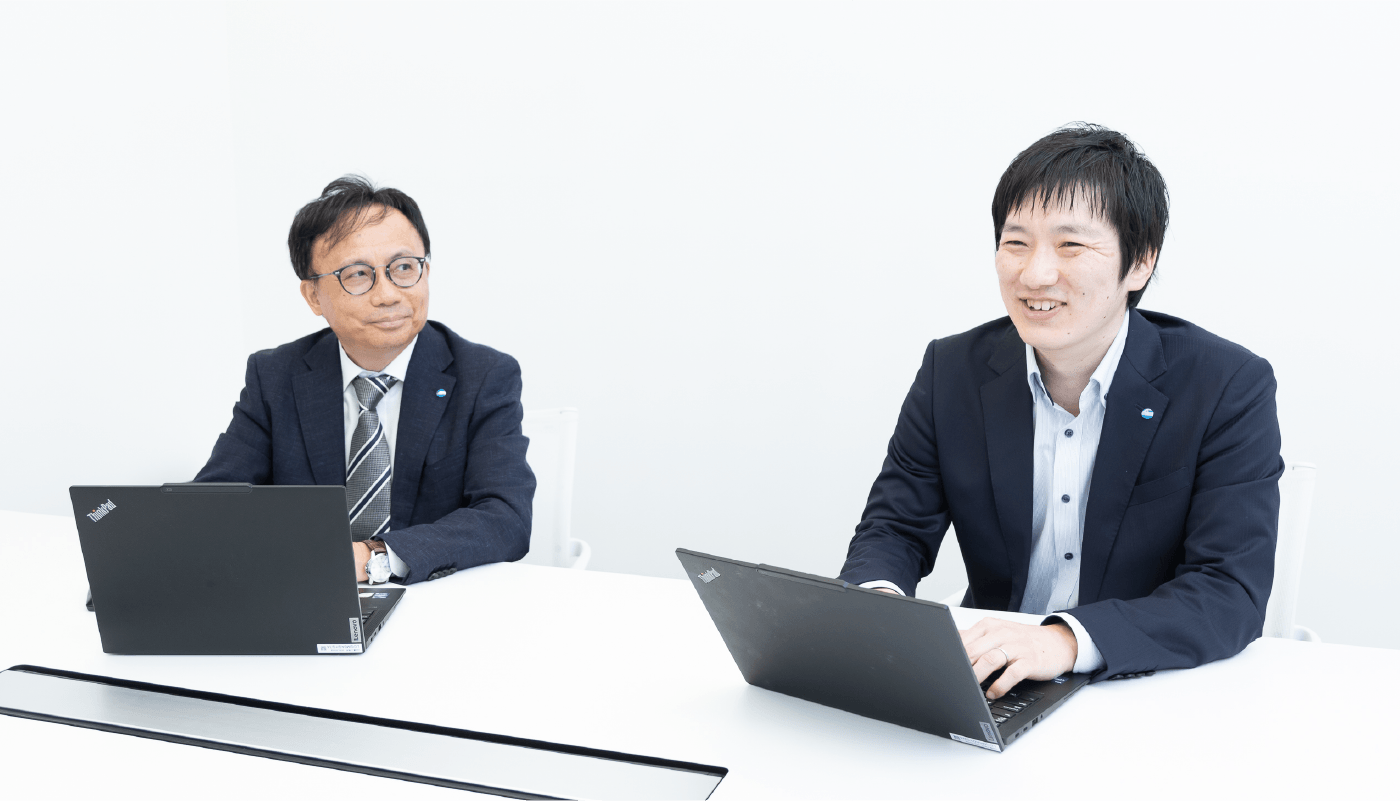
独りよがりにならぬよう
第三者の視点も必要
企画立案や記事制作の過程で気を付けておられることはありますか。
安部氏私どもの言葉で表現、発信していくことに変わりありませんが、独りよがりにならないよう気を付けたいと思っています。コミュニケーション・コンパスさんには取材から記事構成、表現のニュアンスまで私たちの考えを丁寧に汲み取ってサポートしてくれているので感謝しています。何よりメディアとしての経験、視点をお持ちなのは有り難いですし、他企業のオウンドメディアをご支援している客観的な視点もお持ちです。今後もぜひサポートいただければと思います。
西上氏メディア向けに私たちの魅力を分かりやすく伝える努力を続けていきたいと思います。私たちの伝えたいことをメディアの目線、第三者の目線でブラッシュアップいただけるコミュニケーション・コンパスさんの存在は助けになっています。
Imaging Insightの今後の展望をお聞かせください。
安部氏メディアの取材誘致や記事化は引き続き重要です。それに当たっては、より多くの社内人財に登場してもらうほか、お客様の事例を取り上げて社会課題解決への貢献なども紹介していきたいと考えます。
加えて、海外売上の比率が大きい当社として、英語版のImaging Insightも視野に入れていきたいと思います。実は最近、経営層からの指示もあり、英訳した数本の記事を海外のグループ企業へ共有し、ブログの活動を紹介しています。反応を楽しみに待っているところです。
西上氏当社に関心を持つ可能性のある方々は様々な手段によって情報収集にあたる時代です。SNSなどで情報の信頼性が大きく議論される中で、企業自身の発する情報は客観性と信頼性の点において一層の役割を果たしていく必要があるはずです。広報ブログはそういう責務を果たせる存在でありたいと思います。
本日はありがとうございました。
広報ブログ詳細についてはこちら